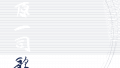(執筆者:生駒大祐)
夏の陽に燒かれて日日をあるばかり石は花々のやうに開かず 杉原一司 (『オレンヂ』掲載歌)
この歌を読んだ時に惹かれたのは、一司が有機的な対象を無機的に、無機的な対象を有機的に描いているからであった。「夏の陽に燒かれ」ながら暮らす(おそらく)自己を「あるばかり」と一個のモノとして存在するように描き、無機物である石に対しては「花々のように開」かないことが意外であるかのように語る。それに類することは本書の解説にも連作「内部について」への言及箇所にて分析されているが、この歌を読んで連想したのは僕の領域である俳句の中でも極めて固有性を持つ句たちである。
うすらひは深山へかへる花の如 藤田湘子
寒鯉を雲のごとくに食はず飼ふ 森澄雄
空蟬をのせて銀扇くもりけり 宇佐美魚目
これらの句はある種の言葉、すなわち季語に対して、過去の名句群の蓄積ゆえの比重の大きさを利用して普遍性を保ったまま無機・有機の間を往還させることに成功しているが、一司の短歌におけるこの倒錯の拠り所は詩における強い実験精神と思想にあったように思う。その点では先に挙げた三句よりも前衛俳句を挙げた方が自然かもしれないし、実際例えば『メトード』掲載歌などはそれに非常に近しいものを感じるのだが、僕はそれらよりもこの歌の方に強く固有性を感じる。それは方法自体が目的化するのではなく、切実な肉声としての言葉がこの歌に現れているからではないか。だからこそ僕はこの歌から炎暑の中に開く石の花弁をありありと想像してしまうのである。
◇生駒大祐(いこま・だいすけ)
1987年三重生まれ。『天為』『オルガン』『クプラス』などを経て現在無所属。イベントユニット『真空社』社員。受賞に第3回攝津幸彦記念賞、第5回芝不器男俳句新人賞等。句集に「水界園丁」(港の人, 2019)。